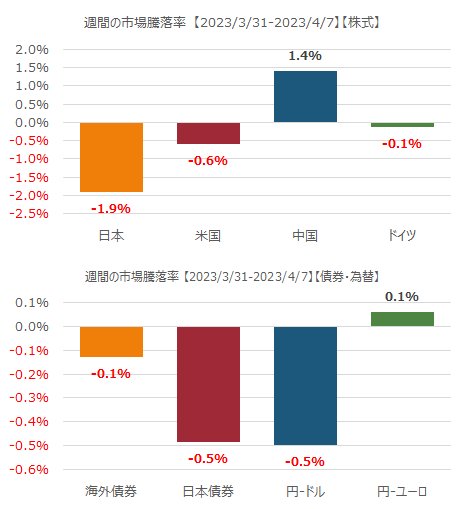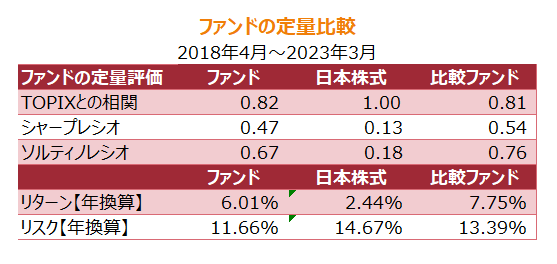2023/4/3 月
米国市場では、テクノロジー株が1%以上値を上げ、銀行株がバイデン政権が厳しい監視を示唆し株価が下落する中、市場全体としては値上がり。KBWの地銀指数は2%以上下落。米国の第4四半期のGDP(3次推定)は2.6%の上昇となった。米国上場のアリババは物流部門を香港でIPOする準備を始めたと報じられ株価が3.5%上昇。欧州市場では、銀行部門の不安が後退し、ユーロ圏のインフレなども減少したことから、株式市場は上昇。銀行部門では、Swedbankが4.9%値を下げ、銀行セクター全体も0.4%値を下げた
2023/4/4 火
米国市場ではOPEC+が予想外に生産を減少させたことにより原油価格が値上がり、エネルギー関連株が値を上げたことからSP500は値上がり。一方、価格を引き下げたにもかかわらず3月の四半期の出荷が前期比で4%しか増加しなかったTeslaは6.1%の値下がり。NASDAQは値下がり。米国政府が提示したメディケア・アドバンテージ料金がよかったため、ユナイテッドヘルスケアが4.6%上昇。そのためダウも値上がり。欧州市場では原油価格の値上がりがインフレにつながるとの懸念から市場は横ばい。一方、原油関連のウェイトの高い英国のFTSEは上昇。テクノロジー株は欧米でのイールドの上昇により値下がり。3月のユーロ圏のPMI指数は、2月から下落
2023/4/5 水
米国では2月の求人がここ2年で最低の水準となり、工場受注も下落したことから、米国市場の主要3指数はいずれも下落。JPモルガンのCEOが投資家向けのレターで銀行危機は続いており、今年1年は影響が出ると伝えた。バンクオブアメリカやウェルズファーゴは2%以上株価下落。産業株の代表とみられるキャタピラーは5.4%値下がり。ディフェンシブなセクターのヘルスケアや公益は上昇。欧州市場では、ユーロ圏の企業物価指数は値下がりしたが、米国の弱い経済データが原油価格の下落を招き、株式市場は下落
2023/4/6 木
米国では民間部門の労働統計が予想以下となり、ISMのサービス指数は予想以上の減速となった。これを受けて米国の株式市場では、ダウは値を上げたが、SP500とNASDAQは値下がり。NASDAQがより大きく値下がり。Googleは、人工知能を使ったスーパーコンピューターを公表し、半導体メーカーのNvidiaは2.1%値を下げた。そのほか、Teslaが3.1%値を下げ、Amazonやアップルも1%「以上値下がり。欧州市場では、ユーロ圏の経済が予想以上に弱いことに懸念を示し、産業やサービスといったセクターが値を下げたが、公益やヘルスケアが値を上げた。市場全体としては値下がり
2023/4/7 金
米国市場では、Googleが人工知能を使った検索を計画しているとウォールストリートジャーナルが報じたalphabetが3.8%、マイクロソフトが2.6%と大きく値を上げ、SP500とNASDAQは値上がり、ダウは横ばい。市場では金曜日に公表される労働統計に注目が集まっている。産業株の指標になっているキャタピラーは2%値を下げた。欧州市場では、イースターの休日を前に、銀行株が大きく値を上げ市場全体も値上がり。ドイツの2月の工業生産は、自動車の生産が増加し、予想を大きく上回るものだった。不動産セクターは2.3%上昇。シェルは液化天然ガスの生産が予想以上になり株価は2.3%上昇