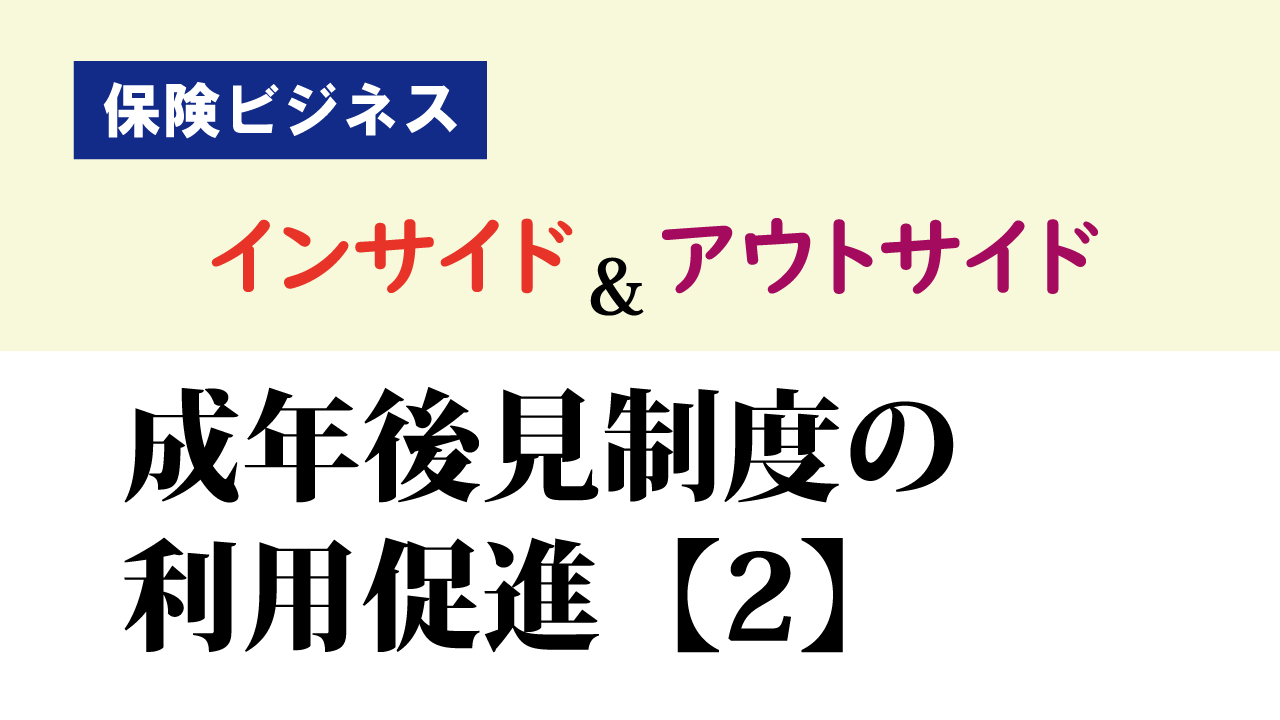(前半はこちら)
後見人の不祥事は後を絶たない。親族が後見人になった場合には、財産を着服するといった不祥事が典型的なものであるが、2011年からの10年間で、親族後見人による不正は被害額全体の94%に上っている。そのため、現在では、裁判所は弁護士などの専門職を後見人に選任する傾向がある。(参考)
後見人の報酬には、基本報酬と付加報酬がある。例えば、遺産相続が発生している場合に、後見人が行う業務には付加報酬が発生する。弁護士であっても、付加報酬を発生させたいというバイアスが発生する。特に、「獲得した財産の〇%を報酬とする」のような報酬体系だと、不必要な“争族”の発生を誘発しかねない。遺産相続が解決された後、弁護士がそのまま身上監護を行うのが適切かという問題もある。
月額基本報酬が2万円だとして、弁護士事務所の職員が、口座にお金を振り込むだけであるなら、後見人はあまり必要ではない。
社会福祉士などが後見人に就任した場合、おこづかいの管理や身上監護は問題ないかもしれないが、相続や不動産の売却などの局面で、どれだけ実のある支援ができるかといえば疑問が残る。
グループホームに入居している精神障がい者のチーム支援の構成員を考えてみよう。司法書士が後見人に選任されたと考える。生活の様子を最も知っているグループホーム、日中の事業所に通所しているのであれば日中事業所も構成員になる。精神科の医師も大切なメンバーになる。訪問看護などのサービスを使っていれば、メンバーに加えたい。遠方であっても親族はメンバーに入ってもらいたい。そして、行政の障がい担当や、生活保護を受けているのであれば保護担当もメンバーに入ってもらう。そうすると、被後見人(障がい者)の意思の推定の精度が上がるであろうし、いつも一緒に過ごしている支援員などがいることにより、本人の意思表出なども向上することが期待できる。
チーム支援のためには、アセスメント(被後見人に関する評価・意見)を継続する必要がある。事務局は後見人が行うべきであろう。前述のガイドラインには、アセスメント表も添付されている。
精神障がい者ではなく、高齢者であればどうなるのか。実は、状況は全く同じである。同じような職種・業種の人が関係者となってチームを構築できる。
チーム支援の事務局を行う人が後見人と考えると、後見人に求められるものは、従来と少し違ったものになるのかもしれない。
一番大切になってくるのは、調整・連絡能力である。法律や医療の専門家は必要であるが、取りまとめ役には適さないかもしれない。
二番目に大切なことは、後見人が交代できることである。相続の例のように、専門性が求められる局面では弁護士や司法書士が後見人になり、相続問題が解決した後は、社会福祉法人などが法人として後見人に就任するといったケースが考えられる。
団塊の世代が後期高齢者に入っていくと、成年後見制度は、さら求められるものになっていく。
この記事は、週刊インシュアランスに掲載されたものを、出版社の許可を得て転載したものです。保険関係者に好評の生命保険統計号もこちらからご購入いただけます。