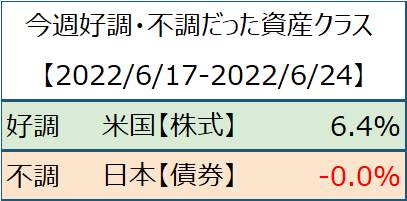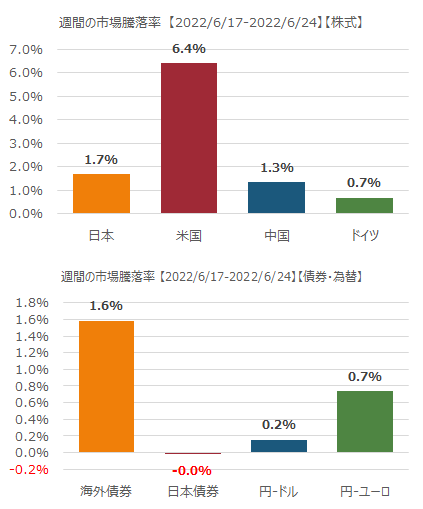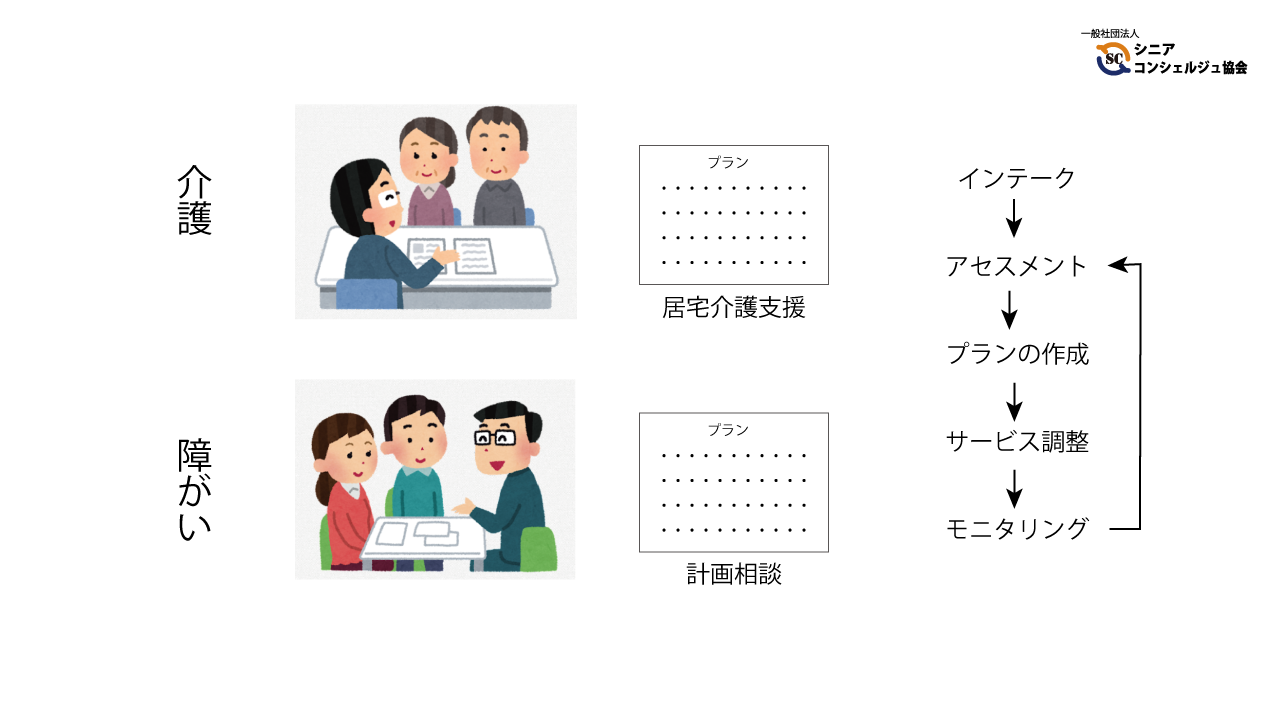2022/6/20 月
米国は株式市場がわずかに上昇したが、SP500の週間騰落率は2020年3月以来の下落となった。また、5月の工場生産高は予想外に下落した。さらに、カンファレンスボードの先行指数は4月に引き続き5月も0.4%の下落となった。ウクライナ問題の影響で、石油・ガスの掘削は6.2%の増加となり、鉱業生産は対前月で1.3%の上昇となった。欧州市場では、市場はわずかに値を上げたが、各国の中央銀行の利上げに伴い経済が減速するとの懸念がぬぐえないでいる。スペインのサンタンデール銀行はCEOが交代し2.3%値を上げた。フィンランドのタイヤメーカーNokian Tyresは2022年の利益予想を引き上げ株価は10.3%上昇
2022/6/21 火
米国市場が休日だったため株式市場は薄商いとなった。欧州市場は株価は少し上昇
2022/6/22 水
米国市場では主要3指数がいずれも2%以上の上昇。エクソンモービルはクレディ・スイスが格付けを引き上げったために株価が6%上昇。エネルギーセクター全体でも5%上昇。CEOのマスク氏が10%の従業員解雇の内容を公表したことから、Tesla株は9%以上の値上がりとなった。AlphabetはNetflixと広告の契約について話を進めていると報じられ、alphabet株は4%以上上昇。Twitterは株主にマスク氏から株式のプライベート化に関する書面が配信され、Twitter株は3%上昇。欧州市場では化学と天然資源関連の株式がけん引して市場は上昇。easyJetは従業員のストライキのため株価が6.3%下落。また、スペインでは発電事業に新たに課税する動きがあり、IberdrolaやEndesaなどが株安になった
2022/6/23 木
米国市場ではFedのパウエル議長のインフレに対応する強い決意を受けて市場はわずかに下落。原油価格が下落したことによりエネルギー株は大きく値を下げる。米ドルとイールドはともに下落。欧州市場は、Fedのコメントを受けて市場は下落。英国ではインフレが9.1%増と40年来の高率になり、FTSEは0.9%の下落となった。不動産、食料・飲料、ヘルスケアなどのディフェンシブなセクターが市場の下落を緩和した。ドイツの化学会社BASFは、2022年の下半期に大きな不況に直面する可能性があることをCEOがコメントし、株価は5.8%下落。鉄鋼会社のアルセロール・ミタル、Voestalpine、Salzgitterなどはブローカーの格付けが下がり、株価が10%以上の下落
2022/6/24 金
米国市場では主要指数は大きく値上がり。イールドが下落したことからグロース株・テクノロジー株が値を戻す。アップル、マイクロソフトともに2%を超える上昇。公益、ヘルスケア、不動産といったディフェンシブな銘柄も上昇。エネルギーはエキソンモービルやシェブロンが3%以上の値下がりとなった。欧州市場では、ビジネス活動指数が下落し、ドイツでは株価が1.8%下落。景気に感応度の高い自動車、鉱業、石油・ガスなどのセクターは2%以上値下がり