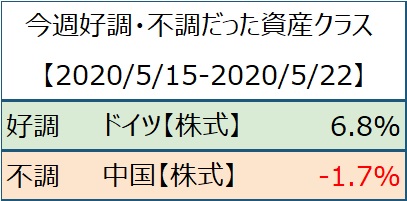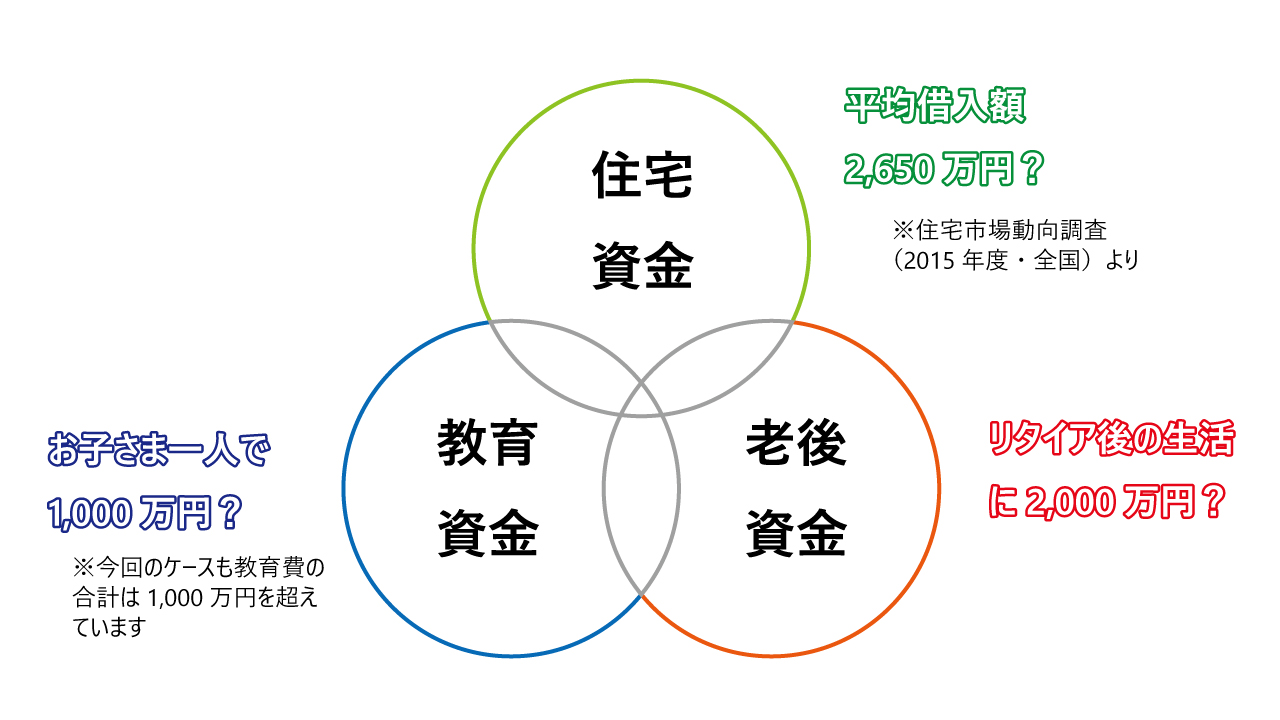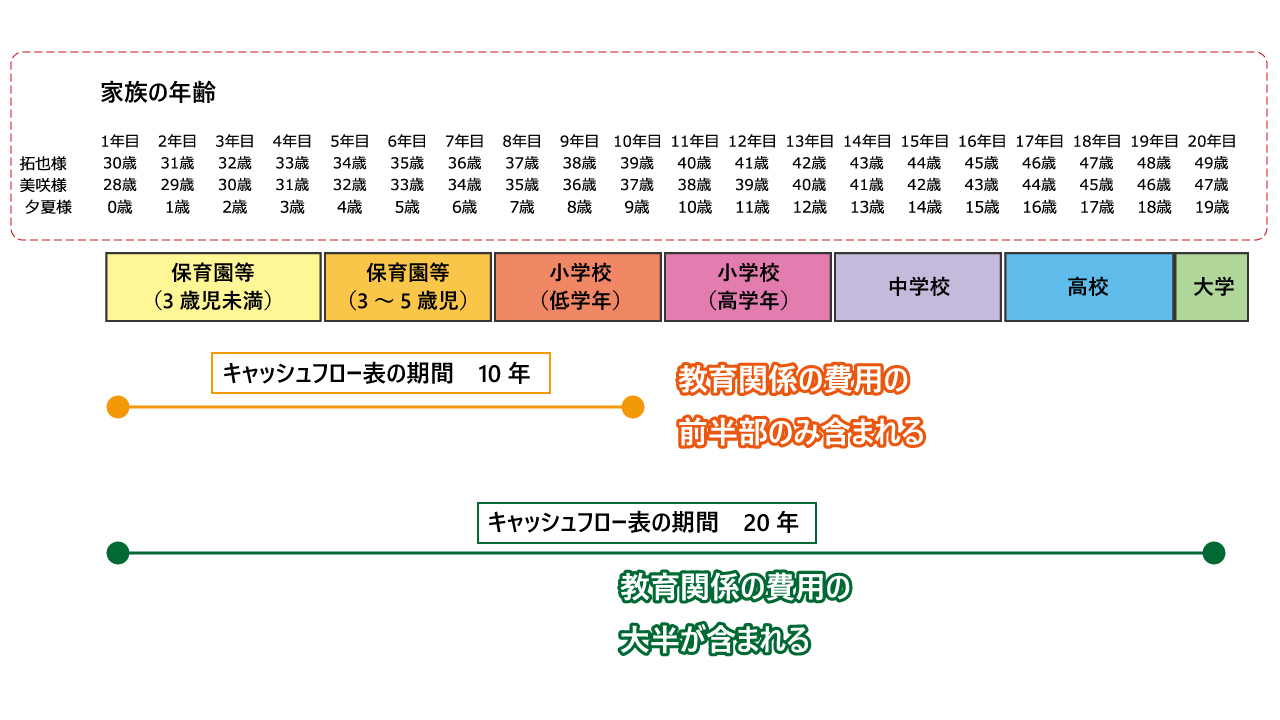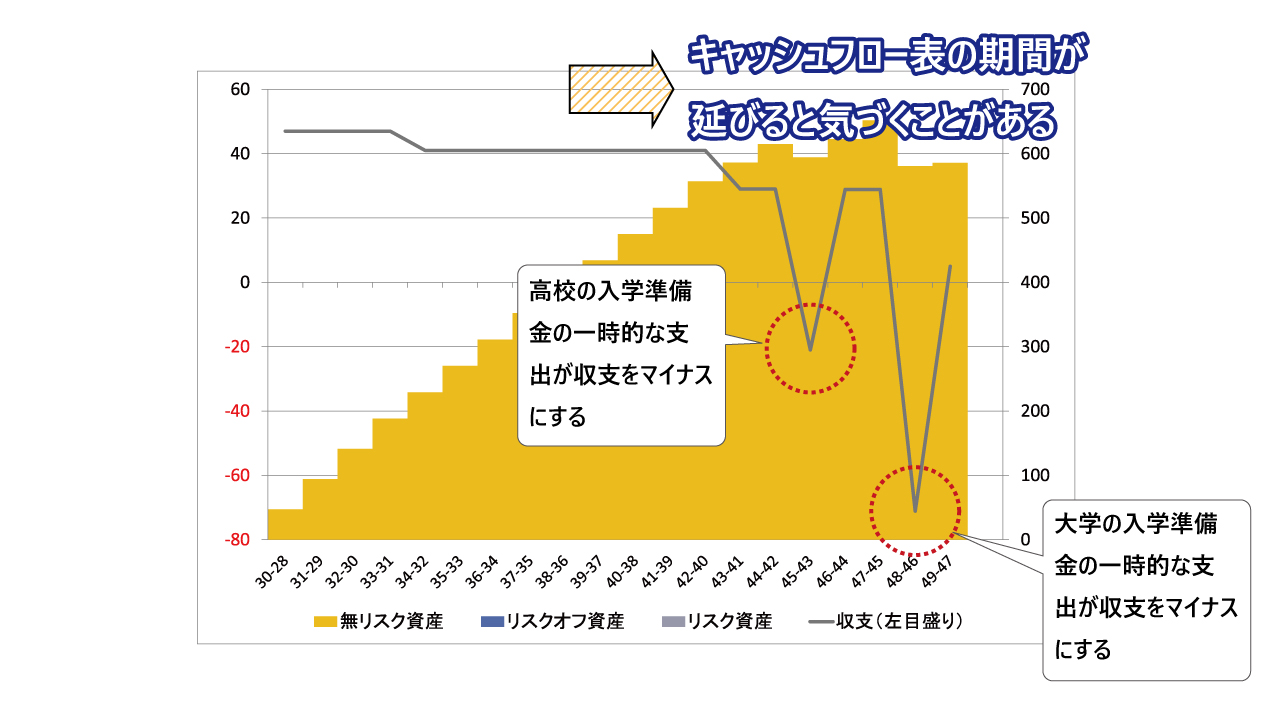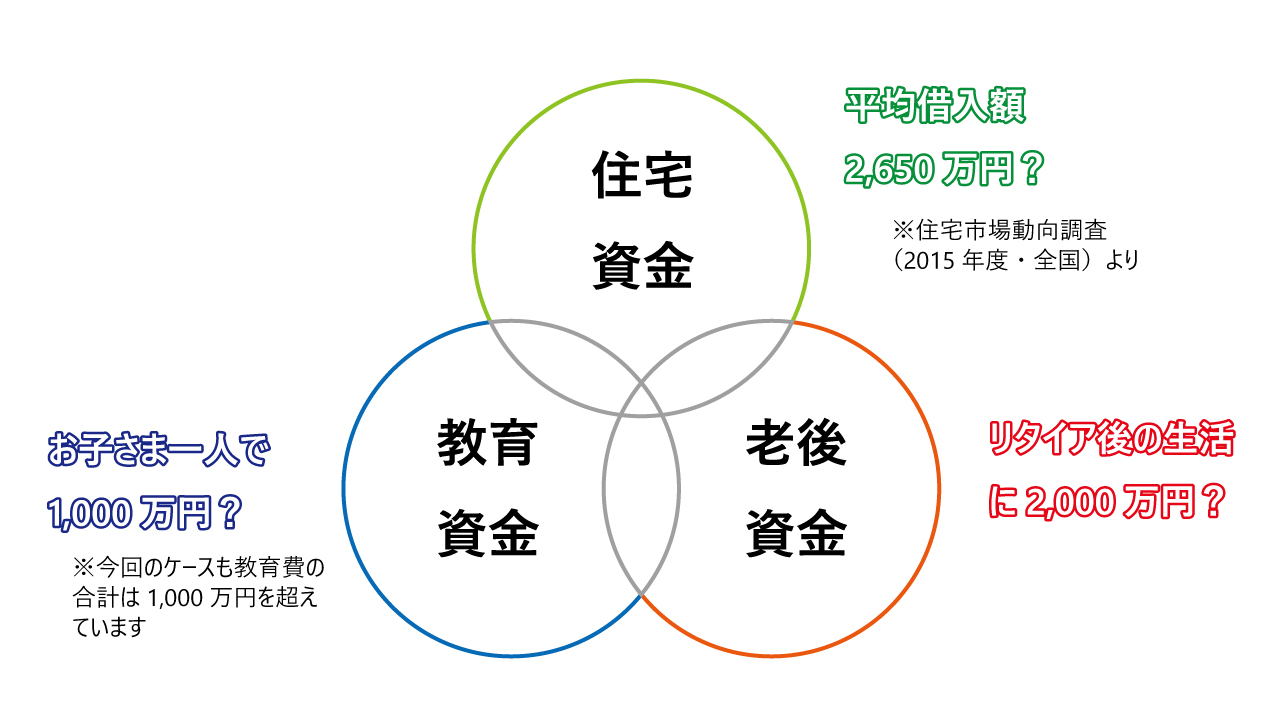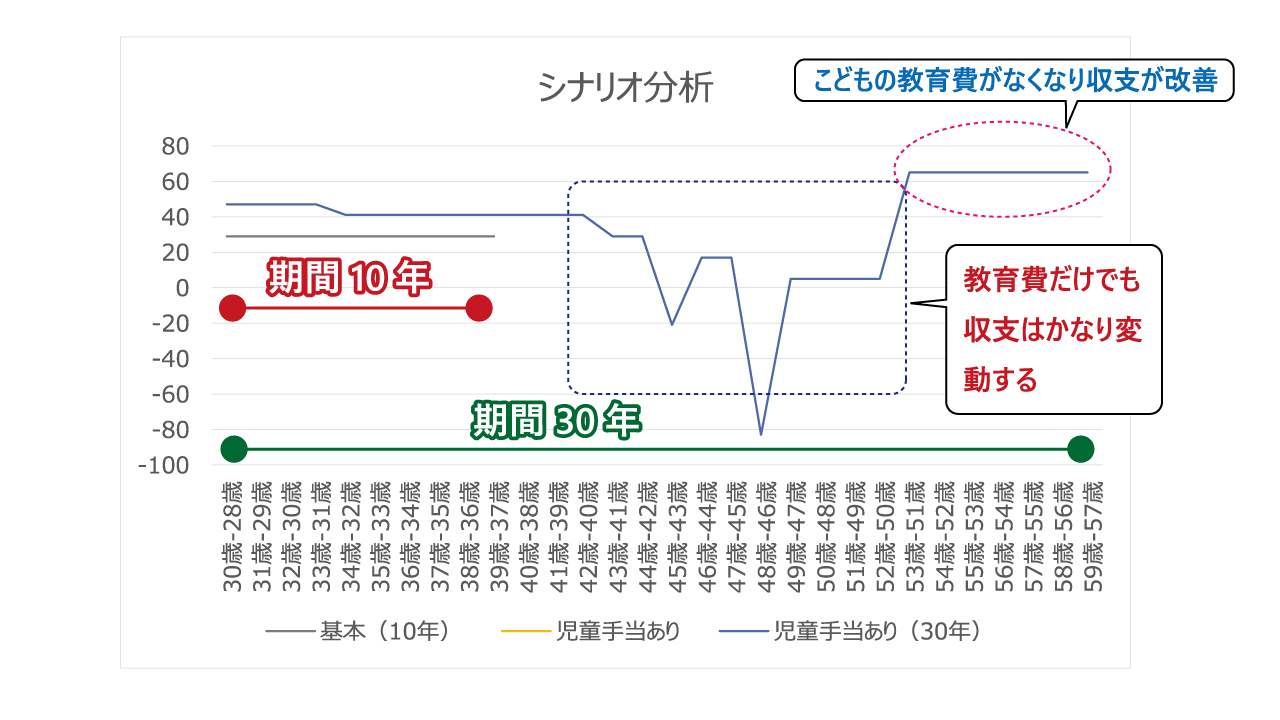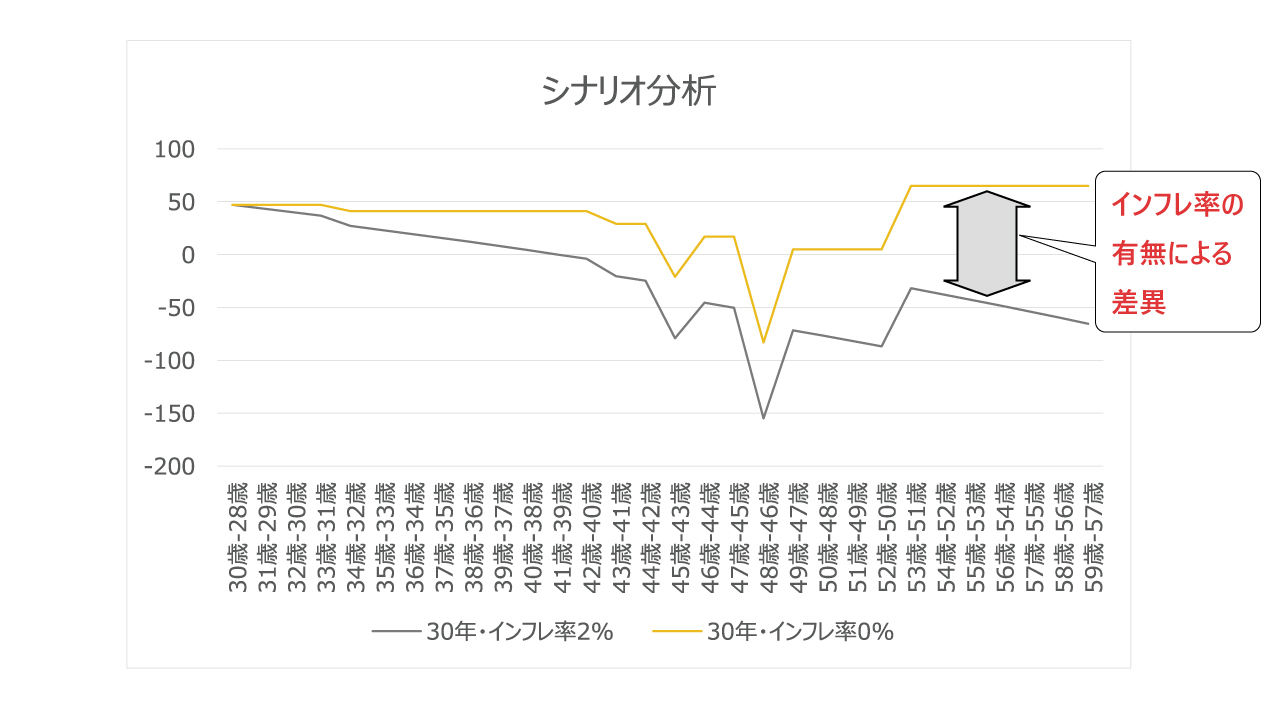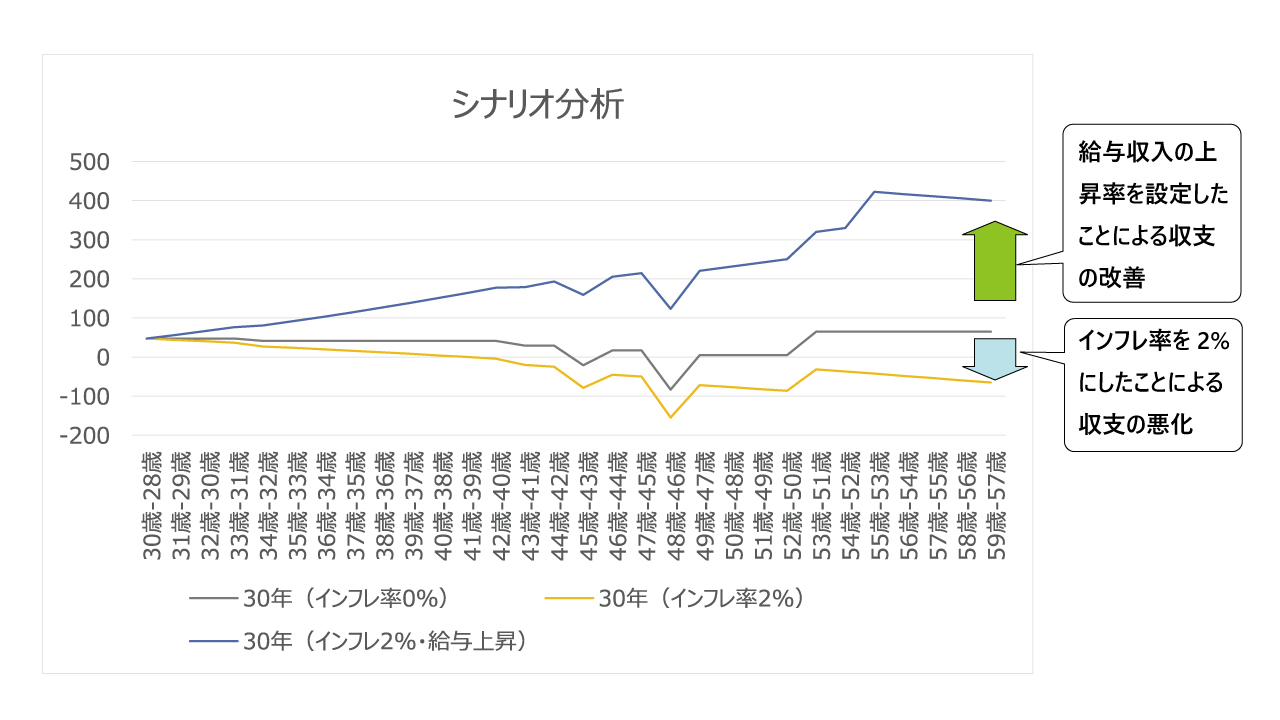2020/5/18 月
米国市場では市場は上下動を繰り返しながら最終的には値を上げる。トランプ大統領は、Huaweiに対して半導体を供給しないように求め、フィラデルフィア半導体指数は2%以上値を下げる。ドイツでは半導体関連のDialog SemiconductorとSiltronicが、それぞれ、3.3%と1%値を下げる。中国は、米国企業の数社を“信頼できない企業リスト”に加えるとコメント。米中対立が先鋭化。米国内ではコミュニケーションと公益部門がけん引。欧州市場では株式指数は上昇。ドイツの第1四半期のGDPは2.2%の下落になったが、中国の4月の工業生産は3.9%増と予想以上の上昇
2020/5/19 火
米国市場では、政府のロックダウン解除の動きとコロナウィルスワクチンの報道で市場は値を上げた。製薬会社のModernaはコロナウィルスワクチンの実験段階での良好な効果をっ確認で来たと公表し株価が20%上昇。カーニバル、ロイヤルカリビアンクルーズなどのクルーズ大手も15%以上の値上がり。GMとフォードは北米の工場を再開させると宣言し8~9%程度値上がり。欧州市場でも景気循環株を中心に値上がり。経済⋀度の再開に向けて鉱業株が8%値を上げる。TotalはEnergias de Portugalから資産を購入することになり株価は7.4%上昇。BPやロイヤルダッチシェルもブレント原油が1か月来の高値になったことから8%ほど上昇。フランスでは金融相が自動車会社への支援を明言し、ルノーやプジョーが値を上げる。ドイツではティッセンクルップが不採算部門の鉄鋼部門を合併させる話が出ており、同株は12.5%の上昇
2020/5/20 水
欧米市場で株式市場は軟化。米国では昨日コロナウィルスのワクチンの実験の初期段階に成功したと報じられたModernaの報告書に疑義が投げかけられ同株は10.4%の下落。ホームデポは四半期の収益が予想を下回り3%下落、Kohl’sも損失が予想以上になり7.7%の下落。ウォルマートはオンラインでの販売は好調であったが株価は2.1%下落。欧州市場では、銀行とテレコム株が軟化。銀行については空売り規制の影響で、スペインのBanco de Sababell、Bankiaが11%前後値を下げ、イタリアのBanco BPMも7.3%値を下げる。テレコムイタリアは第1四半期の損失から2020年通期の利益予想を公表できず8.6%株価下落
2020/5/21 木
米国ではFedが公表した議事録で中央銀行が景気が回復するまで支援を続けるとコメントしていたことから市場に期待感があふれてSP500は2か月来の、NASDAQは3か月来の高値となった。デルタのCEOが航空業界について楽観的な見通しを公表し、航空株指数は5.4%上昇。Targetは四半期利益が3分の1程度になり株価は2.9%下落。欧州市場でも、米国市場にけん引され、また、テクノロジー株にけん引されて上昇。英国のMark & Spencerは10.8%値を上げた
2020/5/22 金
米中関係の悪化が欧米市場に悪影響を及ぼす。トランプ大統領は香港で中国の法律を押し付けるような事態になれば強く反応すると警告。米国市場ではAmazonやマイクロソフトなど最近堅調であった銘柄が値を下げた。Best Buyは販売が予想以下に落ち込み4.4%の軟化。L Brandsは決算は悪かったものの不調なVectoria’s secretを縮小すると公表し株価は18%上昇。米国市場も、欧州市場の市場全体では値下がり。欧州ではオランダのAltice Europeが予想以下の利益となり株価は13.8%下落。英国のホテルグループWhitbreadは新規に10.1億ポンドの現金を調達すると公表し株価は13.4%下落。ドイツのルフトハンザは独政府が90億ユーロの支援を行うということで株価は2.7%上昇