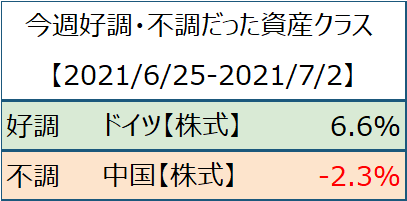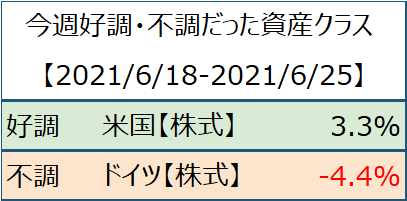2021/6/28 月
米国市場ではSP500が史上最高値を更新。Nikeは、予想を超える収益見通しを公表し株価が15.5%上昇。Fedがストレステストに合格したと公表した、バンクオブアメリカとウェルズ・ファーゴは、それぞれ、1.9%と2.7%株高になった。バイデン政権による超党派のインフラ投資計画は依然として市場を引き上げ続けている。Fedはインフレの目安としているPCEの上昇は対前年比で3.4%と予想とおりの水準であった。Fedexは、雇用が難しくなるため2022年の収益見通しを達成できないとコメントし株価が3.6%低下。欧州市場でも少しだけ株式市場は上昇し史上最高値を付けた。米国のインフラ投資に関連してインフラ関連株が上昇。スキャンダルが発覚したクレディスイスは健全化計画の提出を求められ株価は2.0%上昇
2021/6/29 火
SP500とNASDAQは、好調な決算が予想されるテクノロジー株がけん引して、史上最高値を更新。Facebook、Netflix、Twitterなどが上昇。特に、Facebookは司法当局が連邦取引委員会の訴えを退けたために4%以上の株高に。Nvidiaも5%以上上昇したが、景気感応株は下落。金融は0.8%、エネルギーは3.3%の値下がりとなった
2021/6/30 水
米国市場ではSP500とNASDAQが連日史上最高値を更新。消費者信頼感指数のカンファレンスボード指数は、自動車や家庭用器機の購入が堅調で、の1.5年来の高水準になった。モルガンスタンレーは配当の引き上げを公表し3.4%上昇。ゴールドマンサックス、ウェルズファーゴ、バンクオブアメリカも上昇。モデルナはワクチンがデルタ株にも有効であるとの実験結果を公表し、5.2%株高。アップルのサプライヤーSkywork Solutionsは新型iPhoneの恩恵を被るとして4.5%株高に。アップル自身も株高。欧州市場では、経済センチメントが改善して株価上昇。アディダスは自社株買い計画を公表し2.5%上昇。化学、自動車、金融サービスなどが堅調。旅行関連は、スペインとドイツが英国からの旅行者に対して制限を強化する動きになっていることから株安に
2021/7/1 木
米国市場は、ダウとSP500が値を上げ、NASDAQは値を下げた。SP500は5日連続で史上最高値を更新。金曜日の労働統計を前にADPが民間部門の労働統計を公表。就労人の増加が予想を上回る。エネルギーが上昇し、不動産は下落。ドイツがP-8A哨戒機を8機購入することが報じられボーイングは1.6%の株高。ウォルマートは処方箋不要のインシュリンを販売はじめ2.7%株高。Michron Technologyは2.5%株高。欧州市場では、投資家が利益確定に動いたこととデルタ型ウィルスの不安もあり株安に。自動車株は1.9%の下落となったが、UBSは2021年のGDPユーロ圏のGDP予想を4.3%増から5.1%増に上方修正
2021/7/2 金
欧州市場では原油価格の上昇、OPECの増産が予想以下であったことを背景にエネルギー株が2%以上上昇。旅行・レジャー関連は4日間の下落ののちリバウンドして1.9%上昇。航空株も、EasyJet、 IAG Ryanairなどが1.5%ないし4%の上昇。国内の小売販売が上昇したドイツでは株価指数のDAXが0.5%上昇。英国のAssociated British Foods、フランスのSodexo、デンマークのISSなど食品やケータリングなどの企業も値を上げる。米国市場ではSP500が6日連続の史上最高値の更新となった。Micron Technologyは、テキサスインスツルメントが同社の工場を買収すると報じられたことで、株価は5.7%下落。ISM指数は11月以降で初めて下落。